MTG Arena momir考察
2018年9月20日 TCG全般 コメント (2)
ゲーム内に収録されているカードが限られているから、限定モミールとでも言うべきか、本チャンであるMOのmomirよりは特定の秩序に守られてはいるような気がする。
それでもお互いが最低限のセオリーを解っていればあとは運ゲーだと思うけど、今のところセオリーを解ってない人も多いみたいで、毎回五勝は易い。
ちなみにMOのmomirと違い、初期ライフは20。これが結構重要なのは後述する。
①マナ域のセオリー 確定ザカマ
MO momirと比べると、低マナ域のセオリーはほとんど変わらない。しかし、ある特定のマナ域に確定強クリーチャーがいるため、高マナ域はそこに焦点を絞った戦い方をする必要がある。これを理解していないと勝負の土台に立てない。
MTG Arena内の収録カードに、9マナクリーチャーはたった一体しかいない。その一体が重要になってくる。原初の災厄、ザカマ(以後ザカマ)である。地上から空中まで、戦闘を支配する9/9警戒、到達、トランプル。更に優秀な三つの起動型能力と、モミールのフィニッシャーとして申し分の無い性能を兼ね備えているため、このクリーチャーを出して勝てる状態を作ろうとすることがMTGA momirでの基本戦略となる。
②先手はどのマナ域を我慢するのか 先後の差
まず、先手であれば後手が動かない限りは3ターン目までは動かなくて良い。4ターン目からのmomir起動であれば、毎ターン起動し続けても、ハンデスされない限り先手はザカマまで到達する。9マナが確実にザカマである以上、他のマナ域でどう戦うかというのが始めに問題になることはなく、これがMO momirとの大きな違いだと思われる。
そのため、後手はどのようにして先手に対してプレッシャーを与えていくかというのが戦略上最初に重要になってくる。
3ターン目からの起動であれば、毎ターン起動で後手はザカマに到達する。しかしそこに先手と後手の大きな違い、どちらがザカマを出した後にマナが起きるのかという問題が付きまとう。マナ加速やハンデスが絡まない限り、ザカマを出してマナが起きるのは先手10ターン目が最速で、後手が9ターン目にザカマを出したとしても、先手が山を三枚置くことが出来ていれば後手のザカマは焼かれる。
後手が毎ターン手札を消費してザカマを出していったとしても、先手は土地を寝かせるだけでその対応が可能で、毎ターンカード一枚分ずつ先手が有利になるため、盤面が硬直状態であればそのまま先手が確実に勝利する。
以上の理由から、後手は動きを早めなくてはならない。2マナクリーチャーの中には、上質なものからカスの役にも立たないものまで幅広いクリーチャーが存在するが、その平均値は2/1バニラ以上。2ターン目からmomirを起動し、ライフを詰めていくべきであろう。
※ MTGA momirの初期ライフは20であるため、単純に起動し続けて殴りきるというのがMO momirと比べるとかなり実現し易い
3マナクリーチャーの平均値が2/2バニラ以上、4マナクリーチャーの平均値が3/2バニラ以上であるため、どちらも2~3マナクリーチャーと相打ち相当になりやすいのも後手が2ターン目から動き始めて良い理由の一つで、先手が3ターン目まで我慢する基本戦略を取ったとして、その間後手が2~3ターン目に平均値相当の2/1,2/2を出して殴っていれば、後手4ターン目に先手のライフは16で場には後手の2/1と4マナクリーチャー。多少回避能力持ちを引いたり、進めている盤面をそのまま作っていけば、ザカマが出てくるまでに削りきることが現実的な数字である。
先手の場合、上記を全て考慮した上で考えると、後手が2ターン目に起動してきたら、こちらは3ターン目からの起動が丸そうである。そうした場合、後手4ターン目に先手のライフは18で場には後手の4マナクリーチャー(平均3/2バニラ以上)。今度は先手ザカマまで耐えるのが十分現実的な数字になった。
ただし、先手は3ターン目から起動し続けていては最速でザカマまで到達できない。どこかで一回起動しないターンを作る必要があり、ここで重要になってくるのが7マナ域の混沌の大口である。全体三点火力が付いてくるため盤面が大きく変化するクリーチャーで、もちろん7マナには他にもクリーチャーがいるため確実に出てくるわけではないのだが、勝勢敗勢が一瞬で切り替わるほどの影響力であるため重視すべきだろう。全体三点火力がふってきて嬉しい状況なのかどうかを考え、そうであれば5~6マナのどちらかを我慢、そうでなければ7マナを我慢するのが良い。5~6マナには質の高いクリーチャーも多いが、妙に小粒だったり微妙なデメリットを持っているものも多い。比べて8マナは質の高いものを引きやすく、大きなデメリットクリーチャーもいないため、出来る限り起動すべきである。
ただ、上記は基本的には、という話であって、ライフを詰められ盤面も苦しいような状況では、もちろん最速ザカマを諦めて盤面を作るために毎ターン出来るだけ起動すべきではある。
ちなみに後手には我慢などいらない。最速ザカマには他の粗末な幸運や小さな好プレイなど無意味。毎ターン起動しろ。殺せ。
③先起動か後起動か 後手・・・
メイン1とメイン2のどちらに起動をすべきかという話だが、あまり考えるべき要素は多くない。強襲などを含む、メイン2に起動していたほうが嬉しいクリーチャー達は、盤面を強固にしたりアドバンテージを取ったりするものが多く、これはどちらも先手に求められる要素である。後手はとにかく先起動。速攻クリーチャーを引いた時の場合や、どのようにアタックするかのプランを立てるためにも先に起動したほうが良い。とにかく後手は先手の最速ザカマまでになんとかライフを削るしかないのだ。
④土地の置き方
まずはザカマのために山を三枚置いて平地を二枚置いて森を一枚置く。島と沼は有効な起動型能力持ちクリーチャーを引き当てていない限りはそれが済んでからでいい。
⑤運要素
かなり強いが、とにかく意識すべきは9マナ域で、やってはいけない事は1マナ起動。1マナクリーチャーは、平均値がせいぜい1/1バニラ相当であり、3マナ域の平均値である2/2に相打ちを取れないことが多く、とても損をしやすい。それでいて優良なメリット能力持ちや2/1クラスは極々一部にしか存在しない。
基本的にはこれまで述べてきたことに従って9マナのザカマを意識するだけで、これらを意識していないプレイヤーにはそれなりに高い確率で勝てると思われるが、3マナ以降、どのマナ域にも一発で戦局を決定付ける強烈なクリーチャーは存在しており、回避能力クロックやマナクリーチャー、ハンデス、ドロー、探検持ち等の出現によっては、どのマナ域で動くべきかが大きく変わってくる。
これまで後手がかなり不利であるかのように書いては来たが、先手より先に動くべき立場である以上、必然的にmomirの起動回数も先手より多くなり易く、戦局を作っていきやすいため、あながちそうとも言えない。先手にも、もちろんmomirを積極的に起動して戦局を作っていこうとすることが可能ではあるが、先手唯一の利点である先出しザカマが遠のくため、確率的にはあまり良いことではないと思われる。互いにもったターン数が同じであれば、カードを一枚多く使える後手の自由度の高さが物を言うのだ。
⑥結論
面白いから、皆MTGAやろう。
それでもお互いが最低限のセオリーを解っていればあとは運ゲーだと思うけど、今のところセオリーを解ってない人も多いみたいで、毎回五勝は易い。
ちなみにMOのmomirと違い、初期ライフは20。これが結構重要なのは後述する。
①マナ域のセオリー 確定ザカマ
MO momirと比べると、低マナ域のセオリーはほとんど変わらない。しかし、ある特定のマナ域に確定強クリーチャーがいるため、高マナ域はそこに焦点を絞った戦い方をする必要がある。これを理解していないと勝負の土台に立てない。
MTG Arena内の収録カードに、9マナクリーチャーはたった一体しかいない。その一体が重要になってくる。原初の災厄、ザカマ(以後ザカマ)である。地上から空中まで、戦闘を支配する9/9警戒、到達、トランプル。更に優秀な三つの起動型能力と、モミールのフィニッシャーとして申し分の無い性能を兼ね備えているため、このクリーチャーを出して勝てる状態を作ろうとすることがMTGA momirでの基本戦略となる。
②先手はどのマナ域を我慢するのか 先後の差
まず、先手であれば後手が動かない限りは3ターン目までは動かなくて良い。4ターン目からのmomir起動であれば、毎ターン起動し続けても、ハンデスされない限り先手はザカマまで到達する。9マナが確実にザカマである以上、他のマナ域でどう戦うかというのが始めに問題になることはなく、これがMO momirとの大きな違いだと思われる。
そのため、後手はどのようにして先手に対してプレッシャーを与えていくかというのが戦略上最初に重要になってくる。
3ターン目からの起動であれば、毎ターン起動で後手はザカマに到達する。しかしそこに先手と後手の大きな違い、どちらがザカマを出した後にマナが起きるのかという問題が付きまとう。マナ加速やハンデスが絡まない限り、ザカマを出してマナが起きるのは先手10ターン目が最速で、後手が9ターン目にザカマを出したとしても、先手が山を三枚置くことが出来ていれば後手のザカマは焼かれる。
後手が毎ターン手札を消費してザカマを出していったとしても、先手は土地を寝かせるだけでその対応が可能で、毎ターンカード一枚分ずつ先手が有利になるため、盤面が硬直状態であればそのまま先手が確実に勝利する。
以上の理由から、後手は動きを早めなくてはならない。2マナクリーチャーの中には、上質なものからカスの役にも立たないものまで幅広いクリーチャーが存在するが、その平均値は2/1バニラ以上。2ターン目からmomirを起動し、ライフを詰めていくべきであろう。
※ MTGA momirの初期ライフは20であるため、単純に起動し続けて殴りきるというのがMO momirと比べるとかなり実現し易い
3マナクリーチャーの平均値が2/2バニラ以上、4マナクリーチャーの平均値が3/2バニラ以上であるため、どちらも2~3マナクリーチャーと相打ち相当になりやすいのも後手が2ターン目から動き始めて良い理由の一つで、先手が3ターン目まで我慢する基本戦略を取ったとして、その間後手が2~3ターン目に平均値相当の2/1,2/2を出して殴っていれば、後手4ターン目に先手のライフは16で場には後手の2/1と4マナクリーチャー。多少回避能力持ちを引いたり、進めている盤面をそのまま作っていけば、ザカマが出てくるまでに削りきることが現実的な数字である。
先手の場合、上記を全て考慮した上で考えると、後手が2ターン目に起動してきたら、こちらは3ターン目からの起動が丸そうである。そうした場合、後手4ターン目に先手のライフは18で場には後手の4マナクリーチャー(平均3/2バニラ以上)。今度は先手ザカマまで耐えるのが十分現実的な数字になった。
ただし、先手は3ターン目から起動し続けていては最速でザカマまで到達できない。どこかで一回起動しないターンを作る必要があり、ここで重要になってくるのが7マナ域の混沌の大口である。全体三点火力が付いてくるため盤面が大きく変化するクリーチャーで、もちろん7マナには他にもクリーチャーがいるため確実に出てくるわけではないのだが、勝勢敗勢が一瞬で切り替わるほどの影響力であるため重視すべきだろう。全体三点火力がふってきて嬉しい状況なのかどうかを考え、そうであれば5~6マナのどちらかを我慢、そうでなければ7マナを我慢するのが良い。5~6マナには質の高いクリーチャーも多いが、妙に小粒だったり微妙なデメリットを持っているものも多い。比べて8マナは質の高いものを引きやすく、大きなデメリットクリーチャーもいないため、出来る限り起動すべきである。
ただ、上記は基本的には、という話であって、ライフを詰められ盤面も苦しいような状況では、もちろん最速ザカマを諦めて盤面を作るために毎ターン出来るだけ起動すべきではある。
ちなみに後手には我慢などいらない。最速ザカマには他の粗末な幸運や小さな好プレイなど無意味。毎ターン起動しろ。殺せ。
③先起動か後起動か 後手・・・
メイン1とメイン2のどちらに起動をすべきかという話だが、あまり考えるべき要素は多くない。強襲などを含む、メイン2に起動していたほうが嬉しいクリーチャー達は、盤面を強固にしたりアドバンテージを取ったりするものが多く、これはどちらも先手に求められる要素である。後手はとにかく先起動。速攻クリーチャーを引いた時の場合や、どのようにアタックするかのプランを立てるためにも先に起動したほうが良い。とにかく後手は先手の最速ザカマまでになんとかライフを削るしかないのだ。
④土地の置き方
まずはザカマのために山を三枚置いて平地を二枚置いて森を一枚置く。島と沼は有効な起動型能力持ちクリーチャーを引き当てていない限りはそれが済んでからでいい。
⑤運要素
かなり強いが、とにかく意識すべきは9マナ域で、やってはいけない事は1マナ起動。1マナクリーチャーは、平均値がせいぜい1/1バニラ相当であり、3マナ域の平均値である2/2に相打ちを取れないことが多く、とても損をしやすい。それでいて優良なメリット能力持ちや2/1クラスは極々一部にしか存在しない。
基本的にはこれまで述べてきたことに従って9マナのザカマを意識するだけで、これらを意識していないプレイヤーにはそれなりに高い確率で勝てると思われるが、3マナ以降、どのマナ域にも一発で戦局を決定付ける強烈なクリーチャーは存在しており、回避能力クロックやマナクリーチャー、ハンデス、ドロー、探検持ち等の出現によっては、どのマナ域で動くべきかが大きく変わってくる。
これまで後手がかなり不利であるかのように書いては来たが、先手より先に動くべき立場である以上、必然的にmomirの起動回数も先手より多くなり易く、戦局を作っていきやすいため、あながちそうとも言えない。先手にも、もちろんmomirを積極的に起動して戦局を作っていこうとすることが可能ではあるが、先手唯一の利点である先出しザカマが遠のくため、確率的にはあまり良いことではないと思われる。互いにもったターン数が同じであれば、カードを一枚多く使える後手の自由度の高さが物を言うのだ。
⑥結論
面白いから、皆MTGAやろう。



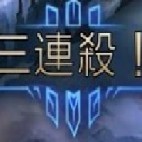
コメント
この記事が書かれた当時の9マナはザカマ確定で合ってるはず